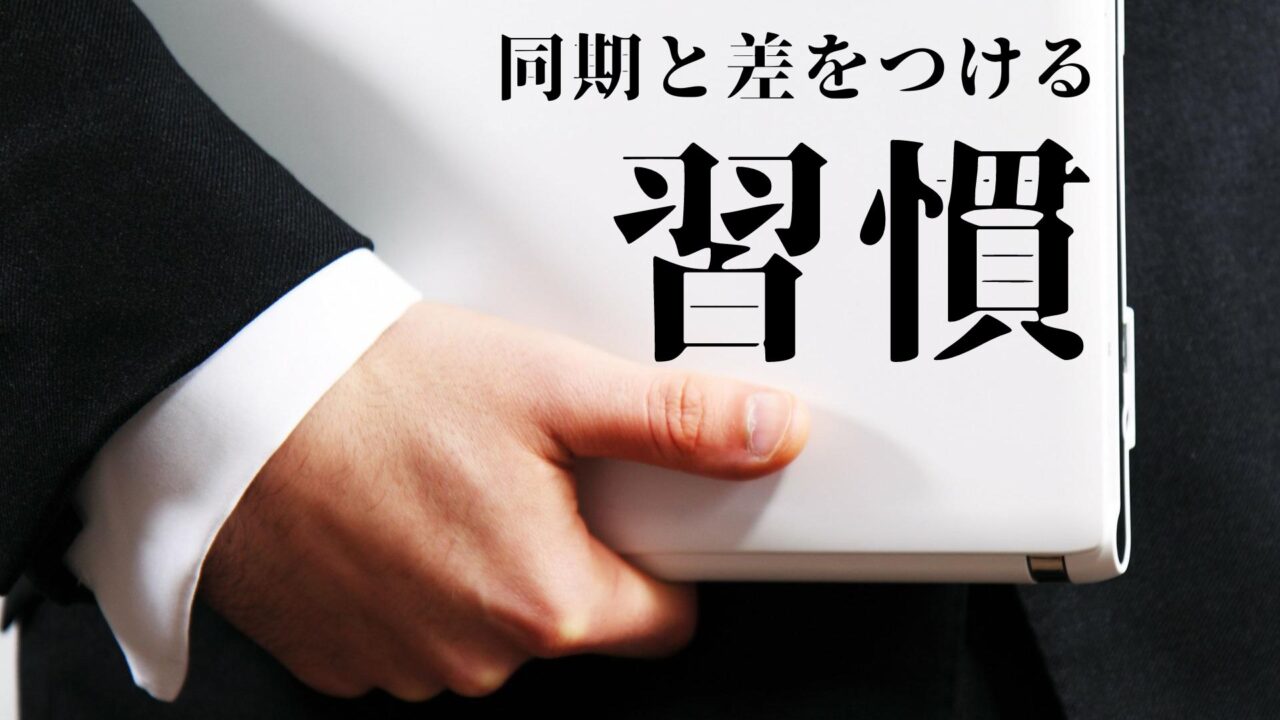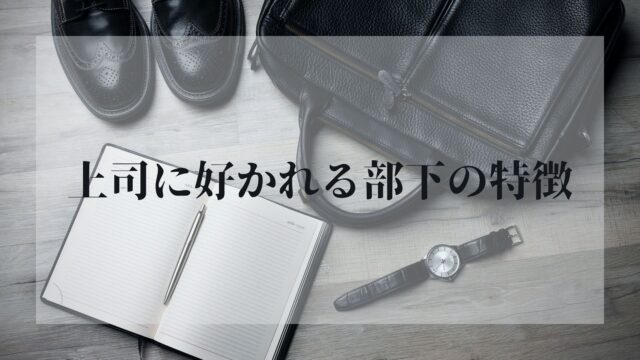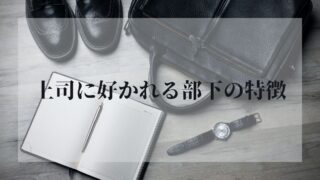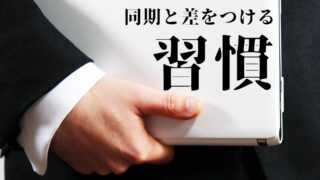こんにちは!たっつーです。
「同期の中で成績トップになるんだ!」
「キャリアアップを目指してバリバリ働いてやる!」
こんなこと思ったことはありませんか?
ただ、若手社員のうちは業務内容が周りとあまり変わらないことが多いので、業務で同期と差をつけるのは簡単ではないです。
今回はそんなあなたに役立つ、同期と差をつける習慣をご紹介します。
日々の仕事の取り組み方ひとつで評価が上がるなんてことも十分ありえます。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
同期と差をつけるための習慣

挨拶をする
挨拶は基本中の基本です。
朝、出社したら「おはようございます」
すれ違った時には「お疲れ様です」
退社するときに「お先に失礼します」
この時、少し大きめな声で目立ってください。
挨拶されて嫌がる人は少ないですし、挨拶から立ち話に、なんてこともあります。
あなたの存在を認識してもらうため、まずはあなたを覚えてもらいましょう。
よく知らない人、元気がない人には話しかけづらいし、上司も仕事をあまり振ってこないものです。
そんな職場では自分の能力も発揮できませんので、挨拶は最重要項目です。
- 少し大きめに挨拶をする
- 元気のない人に仕事は任せない
正しい報連相をする
「報・連・相」
研修などでよく耳にしますよね。
どんなに良い仕事も、上司に知ってもらえないと評価につながりません。
あなたが何かミスをしてしまった時、報連相ができていないと上司に助けてもらえません。
なぜなら上司は知らないから。
こまめに自分の業務の報告をして、わからないことはすぐ相談しましょう。
接触回数が多いほど、その人のことが気になりますし、好意を抱きやすくなります。
逆に報告がないと上司は「大丈夫か?」と不安になってしまいます。
上司や顧客を不安にさせている限り、今より大きな仕事は任せてもらえないでしょう。
「この人に任せておけば安心だ」と思われると、次の仕事に繋がります。
だから現状を共有して相手に不安を抱かせないようにすることが重要なのです。
- 良いことも悪いことも正しく報連相する
- 報連相できていないと、自分が困っていても上司は助けてくれない
報連相については詳しく解説している記事もあるのでこちらもぜひ読んでみてください。

質問をする
分からないことを聞いても怒られないのが若い社員の特権です。
なのに多くの人は「こんなことも知らないと思われるのは嫌だ」と、「分かるフリ」をします。
しかし成果が出せる社員は、分からないことに対して「教えてください」と言えます。
質問するだけでなく「私はこう考えているのですが」という仮説があると、そこから議論が深まり、一つの物事に対してもより深く理解できるでしょう。
そして質問された側は質問者に対して好意的な印象を持つようになります。
上司や先輩と会話をするきっかけが掴めるので、どんどん質問して良い関係を構築しましょう。
- わからないことはそのままにしない
- 質問するときは、自分の考えを伝える
「ありがとう」と言われる仕事をする
あなたの仕事の評価は誰が判断していますか?
もし自分で判断して満足しているようなら、あなたは出世が遅い人のグループです。
仕事の評価を決めるのは相手側です。
あなたがどんなに遅くまで仕事をしても、相手の期待値に達していないと満足してもらえません。
出世が早い人はこのことを意識し、相手の満足度を高めることを目標にクオリティを高める努力をしています。
自己満足の頑張りではなく「何をすれば相手にお礼を言われるか」を逆算して実行するのが高い評価の人の仕事の特徴です。
- 仕事の評価をするのは自分ではない
- 相手の目線で考えて実行する
まとめ

ちょっとした習慣の違いで、自分の評価はガラリと変わります。
「自分は他の同期とは違う」、「同期の中では上の方だろう」という自己評価は捨てましょう。
同期より成長のスピードを段違いにアップさせる方法は、目標をより高いところに置くことです。
同期ばかりを気にして差をつけようとするのではなく、先輩を意識して先輩を超えてやろう、という意識で後悔しない働き方を実践してみてください。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
こちらもぜひ読んでみてください!